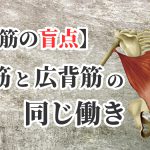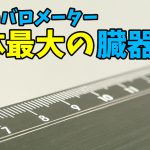運動学の勉強をすると「アイソメトリックス」「アイソトニックス」「アイソキネティックス」という言葉が必ず出てくると思います。これらの3つは "筋肉の収縮運動" の種類です。
最近スポーツの現場で、この "筋の収縮運動の使い分け" についての理解が、選手にも問われてたのを聞いて「あぁ、スポーツ指導も科学的になってきたな~」なんて思ったりしました。
あまり馴染みのない人もいるかもしれませんが、是非抑えておいて欲しい運動なのでご紹介します。
目次
3つの筋の収縮運動の特徴

筋の収縮運動には、3つの種類があります。
その3つの筋収縮の特徴をご紹介いたします。
アイソメトリックス(等尺性筋収縮)
その和名の通り、「筋肉の長さが変わらない運動」です。
外力に対して、筋肉の長さと関節の角度を一定に保ち維持している状態です。
例えば、重力に対して立っている状態、壁を手の平で押すなど、一定の力に対して、一定の力で耐え、エネルギーが拮抗している状態がアイソメトリックスです。
また、インナーマッスルは、体の姿勢や動きを維持する為に、常にアイソメトリックスに働いています。
アイソトニックス(等張性筋収縮)
筋肉が長さを変えながら、外力に対して抵抗する運動です。
関節の曲げ伸ばしが伴う、ほとんどの運動動作がこれにあたります。
また、アイソトニックスは「コンセントリック」と「エキセントリック」の2つのフェーズに分けられます。
コンセントリック(求心性筋収縮)
筋肉が縮みながら、外力に抵抗するフェーズです。
&nsp;
例えば、肘を曲げると上腕二頭筋(力こぶ)が "コンセントリック収縮" を起こします。
エキセントリック(遠心性筋収縮)
筋肉が伸ばされながら、外力に抵抗するフェーズです。
例えば、肘を伸ばすと上腕二頭筋が "エキセントリック収縮" を起こします。
この様に、アイソトニックスには2つのフェーズがあります。
また関節の構造上、関節角度によって強度が異なります。
例えば、上記の肘の曲げ伸ばしでは、肘と物体が最も離れる、肘関節90度の局面が最も強度が高くなります。
この局面を "スティッキングポイント" と呼びます。
アイソキネティックス(等速性筋収縮)
関節の曲げ伸ばしが伴い筋肉の長さが変化するものの、スティッキングポイントが存在せず、一定の外力が加わる運動です。
この運動は、日常的な動作では起こり得ない運動です。
例えば、水泳がこの運動に該当します。
水の中で、どの関節の角度でも、一定の負荷が掛かかります。
陸上では特殊な装置を用いない限り、アイソキネティックスに運動する事はありません。
ゴムバンドやチェーントレーニングなどで近い状態を作ることは可能です。
スポーツ動作と筋収縮

スポーツ動作で主に使う筋収縮は、「アイソメトリックス」と「アイソトニックス」です。
例えば、
トランポリンで高く跳ぶ為の脚の動作では、最初は反動をつける為に「アイソトニックス」が使われます。
スプリングが十分にしなってきたら、高く跳ぶ為には、脚の関節を曲げずに「アイソメトリックス」に運動することでトランポリンのエネルギーを活用する事ができます。
また、すべての運動動作では「体幹部を固定して手足を動かす」この様に、アイソメトリックスに使う部位と、アイソトニックスに使う部位が必ず存在します。
近年、スポーツ動作も「物理的な効率」が求められる傾向がある為、これらの筋の収縮運動の基本知識はトレーナーのみならず、スポーツ選手は抑えておいた方が良いかもしれません。